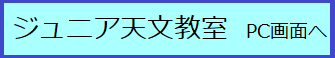(2025/7/18 掲示、敬称略)
*2025年度、月例講座(第3土曜日)
*2025年度、月例講座(第3土曜日)
7月19日 すばる望遠鏡26周年の歩みと誰でも楽しめるデジタルコンテンツ
国立天文台ハワイ観測所 臼田-佐藤 功美子
講演要旨(PC画面)
8月16日 (仮題)地球接近天体と日本スペースガード協会の活動
日本スペースガード協会 浅見 敦夫
概要紹介(準備中) 講演要旨(準備中)
9月20日 小さな天体が起こす大事件
-新星,超新星,γ線バースト-
東京大学理学系研究科
ビッグバン宇宙国際研究センター 茂山 俊和
概要紹介(準備中) 講演要旨(準備中)
(2025年度後半プログラム)
(csvファイル、日時・タイトル・講演者)
●2011~2023年度、講演詳細記録
国立天文台ハワイ観測所 臼田-佐藤 功美子
講演要旨(PC画面)
8月16日 (仮題)地球接近天体と日本スペースガード協会の活動
日本スペースガード協会 浅見 敦夫
概要紹介(準備中) 講演要旨(準備中)
9月20日 小さな天体が起こす大事件
-新星,超新星,γ線バースト-
東京大学理学系研究科
ビッグバン宇宙国際研究センター 茂山 俊和
概要紹介(準備中) 講演要旨(準備中)
(2025年度後半プログラム)
*過去1年の講演
→ 別ページへ*各種情報(大画面)
●月例講座,2023年度までの全記録(csvファイル、日時・タイトル・講演者)
●2011~2023年度、講演詳細記録
*内部連絡用(大画面)